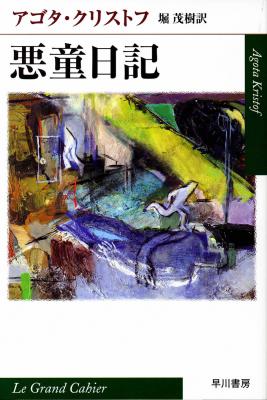
アゴタ・クリストフ著作『悪童日記』を読了。
まずはアゴタ・クリストフという作家について浅学ながらも少し。
ハンガリー生まれでありながら21歳の時に動乱から逃れるためにスイスへ移住。移住先で作品を書くもそのほとんどが発表されず、現地の言語で作品を書く必要があると感じた彼女はフランス語で小説を書き始める。
そして発表された『悪童日記』は評価され、40ヶ国語に翻訳され世界的に彼女を名を知らしめた。
本作『悪童日記』は戦時中に郊外のおばあちゃんの家へと疎開してきた双子「ぼくら」がノートに書きつけた記述、という形式で書かれている。彼らは名前も明示されず常に一緒に行動し、どちらがどちらか区別もなく、終始一人称は複数形の「ぼくら」である。そして異様なのが作中で彼らが掲げた記述のルール、「主観と感情を排除した記述」である。
例えば「この町は美しい」という記述は正確ではないので書かない。何故なら「ぼくら」からすれば確かにその町は美しく見えたとしても、別の人からすればそれは美しくはないかもしれないから。
後天的に習得したフランス語を使った小説執筆の影響か、勿論意識的なものもあるだろうけれども、この一人称と極めて情緒性を排除した文章表現は物凄いインパクトを放っている。そして面白い事に、ヒロイックな感情もセンチメンタリズムも全てを拒否した、そんな淡々とした文章だからこそ少年達が目にする事象、出会う人達、直面する現実のかなしさや切なさや残酷さが浮き上がってくる。
双子の「ぼくら」も強烈なインパクトを放っている。
彼らは恥部に毛も生え揃っていない児童でありながら「苦痛に耐える訓練」「感情を殺す訓練」「不動の訓練」「乞食の体験」をし、必要なものはどんな手段を使っても自分達で手に入れ、自分達で学習をし、力をつけ、生活していく。夫殺しの過去を持つおばあちゃんはそんな双子を「雌犬の子」と呼び、労働せねば食事も寝床も与えない。けれど双子は嘆くでもなくストイックに自分達の訓練を続け、成長して生きていく。
「ぼくら」は一見サイコパス的な無感情さ、倫理観の欠如を以てして目的を達成する。盗みや恐喝、殺人さえも犯す。けれども彼らはサイコパスではない。彼らは自分自身に忠実な等身大の人間には一種の共感を以て接するし無条件の援助さえも惜しまない。外界を、周りの人間を内に入れないだけで拒絶しているわけではないのがみてとれる。
三部作の一作目である本作、感想が書きづらい。けれども本当に面白い良い作品だと思った。一晩で一気に読んでしまった。勿論続編も読んでいこうと思っている。
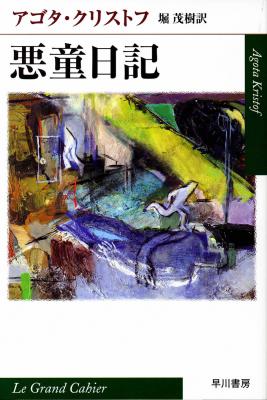
コメント